サイト内の現在位置
設計プロセス ~部品技術~ (対談編)
人工衛星やロケットに搭載する機器(以下、宇宙機器)には、耐放射線性能など宇宙環境に耐えうる性能が求められる。それはつまり、宇宙機器に使われるさまざまな「部品」にも、厳しい宇宙環境に耐えうる品質が求められることを意味する。NECスペーステクノロジーにおいて、この宇宙用部品の品質管理や開発などを担うのが「部品技術部」だ。同部門で“部品のエキスパート”として活躍するOhtsuka Hiromichi氏とHashimoto Akira氏のお二人に、「部品技術」の仕事とそのおもしろさについて語ってもらった。

「部品技術部」が担う4つの主な業務

――まずは「部品技術部」がどういう業務を担っているのか教えていただけますか?
Ohtsuka:私たちが所属する「部品技術部」は、宇宙機器に使用する部品を専門に扱う部門です。業務は多岐にわたりますが、主に「新規部品採用」、「部品開発」、「部品ベンダと部品情報の管理」、「部品の信頼性品質管理」の4つの業務を紹介いたします。これらの業務を通して、当社が開発する宇宙機器のQCD(「Quality:品質」「Cost:コスト」「Delivery:納期」)を担保しています。
――「4つの業務」はそれぞれどんなことをするのでしょう?
Ohtsuka:1つ目の「新規部品採用」は、その名の通り新しい部品の採用を決定する業務です。お客様からの要求を満足するため、新しい機器設計や既存の機器の部品の置き換えで新規部品が必要となることがあります。新しい部品の採用は、性能/材料/構造/実装/調達の観点から関係部門と連携し、決定します。採用可となれば仕様調整/購入仕様書作成などを行い、調達へと進めていきます。

Hashimoto:採用可否の重要なポイントは、宇宙環境に耐えうるかどうかです。真空下での動作や耐放射線性能、排熱、温度変動、長寿命など宇宙で使う部品ならではの厳しい条件をクリアしたものでないと採用できません。ここが民生品との大きな違いです。
――2つ目の「部品開発」はどのようなことを?
Ohtsuka: 開発者が機器の開発/設計をしていく中で、既存部品では希望する特性を満たせない場合があります。その際、機器に合わせた仕様を部品ベンダの技術者と協力して作成し、製品化しています。
また、当部門には、半導体の回路設計に従事していた技術者が在籍しており、チップの設計から担当することもあります。
――3つ目の「部品ベンダと部品情報の管理」は、どのような業務でしょうか?
Ohtsuka:「部品ベンダの管理」は、主に、不具合防止活動、製造状況の把握、動向調査があります。
これらを実現するためには、部品ベンダと密にコミュニケーションをとることが必要です。このため、部品ベンダを訪問する際には、必ず製造現場に入り、担当の技術者が抱える悩みを一緒に解決することで、不具合の未然防止と製造状況の把握に役立てています。また、技術動向を技術者から直接伺うことで、当社の部品戦略に活用しています。
「部品情報の管理」は、基本情報(部品番号や品名)、部品仕様(定格、電気特性など)、部品の信頼性品質/放射線含む試験データなどの情報を入手し、システムにて整備しております。また当社では生産効率や品質向上、コスト削減に取り組む改善活動を実施しており、その一環として現場からの問い合わせや部品不具合の事例集を作成し、知見を残しています。
――4つ目の「部品の信頼性品質管理」は?
Ohtsuka: 宇宙用部品は、多岐にわたる専門的な知識が必要になるとともに、極めて厳しい環境条件での長期間にわたるミッションを成功させるため、主に①スクリーニング試験、②ロット保証試験、③放射線試験に合格することが要求されています。
①スクリーニング試験は部品の初期不良を除去する試験です。万が一宇宙空間で部品が壊れてしまっても、なおすことができません。このため、初期不良の部品は排除する必要があります。②ロット保証試験は製造/検査ロットを保証する試験です。様々な機器に使われている部品に問題があった場合、波及効果は非常に大きくなります。そのような事態を防ぐため、ロット保証試験により波及効果を最小限にしています。③放射線試験は、運用環境での放射線耐性を把握するための試験です。宇宙空間ではエネルギーが大きい放射線にさらされます。このような環境では、部品が異常動作をすることがあり、放射線試験で事前に確認しています。
Hashimoto:4つの業務のうち、この「信頼性品質管理」が特に重要だと考えています。宇宙用部品は、極めて厳しい宇宙環境下でのミッション成功の鍵を握るものです。人工衛星やロケットが実現すべきミッションや、お客様からのニーズに応じた最適なソリューションを提供するためにも、部品の「信頼性品質管理」は極めて重要となります。そのため、部品の信頼性品質要求に対して、主に新規ベンダの品質監査やトレーサビリティおよび試験項目/試験結果が記載された部品納入データの確認を行っています。
――お二人はそれぞれどのような役割を担っているのでしょう?
Ohtsuka:我々二人とも、この4つの業務を担っており、大まかな業務内容は同じです。ただ、担当する部品の品種は異なり、私は、「LSI(大規模集積回路、Large Scale Integration)」を主に担当しています。LSIはFPGA (Field-Programmable Gate Array)、メモリ、MPU(Micro Processing Unit)などがあり、人間で例えると情報を処理、制御や記憶する脳の役割にあたる部品です。
Hashimoto:私は電流の方向や流量を制御する用途などに使われる「ダイオード」を中心に担当しています。当社では宇宙用部品をいくつかの品種に分けており、「部品技術部」では、品種ごとに担当者を置く形をとっています。
多様なキャラクターが集まる部門
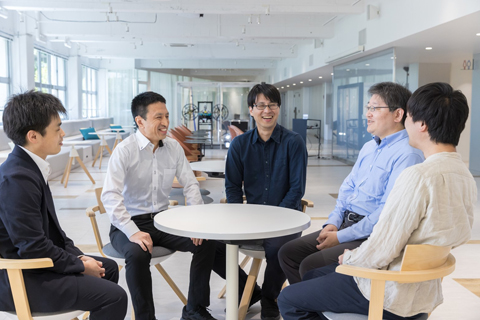
――「部品技術部」には、どんなタイプの人が集まっていますか?
Ohtsuka:新卒でNECスペーステクノロジーに配属された人もいれば、NECの宇宙以外の領域から移ってきた人もいます。また、私もそうですが、キャリア採用で他社から転職してきた人もいます。多様なバックグラウンドがある中で、論理的思考の人、計算や分析が得意な人、物事を客観的に見るのが得意な人、細やかな気配りができる人、コミュニケーションスキルが高い人など、さまざまなタイプの人が集まっている印象です。
Hashimoto:ちなみに私自身は、もともと社内の電気設計部門から移ってきたこともあって、最悪なケースを想定して安全な方に行きたい慎重派だと自覚しているのですが、Ohtsukaさんから見てどうでしょう?
Ohtsuka:そんなところもあるかもしれません(笑)。Hashimotoさんは同世代なこともあって、すごく相談しやすい相手ですね。
Hashimoto:Ohtsukaさんは、10年ほど前に他社から転職されてきたわけですが、「部品技術部」でのキャリアは私より長くて、すっかり頼りにしているところがあります。いろんな面できっちりされている印象ですね。
――部門全体の雰囲気はどんな感じでしょう?
Ohtsuka:雰囲気は穏やかで、働きやすいと感じています。「部品技術部」は、プロジェクトや品種ごとに担当が分かれていますが、情報共有を密に行うチームワークが優れている組織だと思っています。
また、上述の通り、宇宙事業経験者だけでなく、別の事業から来られた方々も活躍できる環境です。
Hashimoto:ベテランの方も多く在籍していて、そういった方々に相談しやすい雰囲気もありますね。
Ohtsuka:加えて「部品技術部」は、業務の性質上、社内のほとんど全ての部門と一緒に仕事をしますが、他部門の方々にすごく助けてもらい、協力することで、ワンチームとして業務にあたれていますので、会社全体としても働きやすい環境であると感じています。
「知識が増える」ことが技術者としての喜び
――お二人ともキャリアを長く積まれていますが、その中で「部品技術」の仕事のどのようなところに魅力を感じていますか?
Hashimoto:以前、電気設計をしていた時には、宇宙部品の中身はブラックボックスでした。しかし「部品技術部」に入り、部品を扱うようになってからは、部品の中身が見えてきました。電気設計をしていた時にはわからなかった部品のことがわかるようになる、そこに楽しさを感じています。
Ohtsuka:「知識が増える」楽しさは確かにありますね。私はそこに加えて、部品技術の世界が常に進化していることもあって、技術的な挑戦が多い点にも魅力を感じます。
Hashimoto:新しい材料や技術、部品の製造プロセスの開発など、部品技術の世界はどんどん進化していますよね。
Ohtsuka:さらに最近では、航空宇宙用部品だけでなく、車載部品など民生部品の適用も進み、これまで以上に幅広い知識が求められるようになりました。そうした「新しい動き」に対応することは大変ではありますが、その分、自分の知識増や技術の向上につながります。その知識を新規機器開発に採用されることに技術者としての喜びを見出しています。
社内外の関係者とも一致団結し、1つのものを作り上げる楽しさもありますね。
Hashimoto:同感です。「部品技術部」は社外の人とも深く関わる部門です。そのため、何か問題があった時には社内外の関係者と協力し合いながら問題解決していくので、その中で大きなやりがいや達成感が得られる仕事だと感じています。
海外メーカーとの文化の違いに苦労することも

――逆に「部品技術」の仕事で、「辛いな」と感じるのはどういった点でしょう?
Ohtsuka:新しい部品の短納期での開発や部品の不具合で長期間解決できなかったことです。そうした時には、お客様や開発者からの要求はもちろん、スケジュールやコスト面でもプレッシャーがかかってきます。そんな中でも我々は信頼性品質を考慮しながら情報を集め、部品開発や不具合対応を進めなければいけません。これまでは、部品ベンダ、社内メンバーとの密なコミュニケーションにより、協力して解決してきました。
Hashimoto:私は海外の部品ベンダとのやり取りが多いのですが、不具合に対する根本的な考え方が日本の企業と異なるため、意思疎通で戸惑うことが多いですね。例えば、我々日本企業では、何か問題点があれば、その問題がなくなるように作り込んでいきます。しかし、その海外ベンダでは”不良は起きるもの”と織り込み済で、出荷前までのどこかで不良品をはじくプロセスとしています。そのような考え方の違いがあるため、日本国内のお客様への不具合の予防の説明で苦労することもあります。
――具体的にどう説明しているのですか?
Hashimoto:何か不具合が起きた時には、海外ベンダから不具合要因などの情報をもらい、それを元にお客様が理解できる表現にし、海外ベンダ側に了承を得た上で、お客様に提出します。本来ならば、当社に対し、海外ベンダから不具合要因とそれをなくすための対策を説明頂きたいところですが、”不良は起きるもの”と織り込み済という考え方であり難しい。
ただ、先ほどお話したように、部門内には海外ベンダとの対応に慣れたベテランも多く、そうした方々に相談すれば、的確なアドバイスをいただけます。そうした環境は、ありがたいなと思いますね。
不具合は成長につながる “財産”

――これまでのキャリアで、最も印象に残ったプロジェクトについてお聞かせください。
Ohtsuka:部品技術部の業務は様々なプロジェクトに関連しているため、プロジェクトを絞ることはできませんが、新しい部品の短納期での開発や部品の不具合で長期間解決できなかったことは印象に残っています。特に部品の不具合は波及範囲が広い場合もあり、プロジェクトの遅延、コスト増、品質の低下などに影響してしまいます。
Hashimoto:そうですね。私もいろいろな宇宙機器に波及しそうな不具合が起きたプロジェクトが1つあって、その時の経験が一番印象に残っています。ある半導体部品を大量に購入したのですが、これを使っている宇宙機器が不具合を起こしたのです。すでにいろいろな機器に使われていましたので、各機器で問題が発生していないか一つひとつ確かめなければならなくなりました。
Ohtsuka:宇宙用部品はトレーサビリティ管理が確立されているので、調達した部品の材料、製造や試験の詳細を把握できるだけでなく、機器製造に使用した部品の情報も追跡できるようになっていませんか。
Hashimoto:はい。情報を集め、試験結果などのデータを照合しながら問題が発生していないか確認してもらいました。結果として、そこまで影響が波及することはなかったのですが、多くの人に迷惑をかけたので、肉体的にも精神的に非常に辛かったですね。ただ、上司や関係部門に助けてもらう中で、自分の考え方とは異なる、いろんな人の考え方を知れたのはよかったです。不具合を通じて学ぶところが多く、大きな成長につながったかなと感じています。
Ohtsuka:難しい課題解決を経験すると、知識や知見が深まりますし、記憶にも強く残りますよね。また、次に同じようなことが起こった際に活かせますし、得られた情報を積極的に社内に共有することで、個々の経験が会社全体の知識や知見として蓄積されます。不具合は単なる課題ではなく、成長につながる貴重な“財産”とも言えるのかもしれません。
さらに「ポジティブな業務」に注力したい

――最後に、お二人が今後どのようなところに力を入れていきたいかをお聞かせください。
Ohtsuka:私は、3つ目の業務としてご紹介した「部品ベンダと部品情報の管理」の中にある新しい部品情報の入手に力を入れていきたいです。なぜかというと、先ほどから部品の不具合のお話をしていますが、不具合の対応はどちらかというとネガティブな要素です。こうしたところに自分や会社のリソースを割くのではなく、新しい機器開発のための部品調査などポジティブな業務に時間を使いたいからです。具体的には、新規および既存部品の市場調査を通じて、自分が担当するLSI(大規模集積回路)の主要部品や周辺部品に関する世界的な動向を把握したいです。また、部品担当者全員が本活動をすることによって高性能な新製品を生み出しお客様に最高の価値を提供していきたいと考えています。
Hashimoto:私も同じくポジティブな業務に力を入れたいです。例えば、現状、我々部品技術部からは、担当した部品がどの宇宙機器で、どんな使われ方をしているのかがあまり見えていません。こういった課題を改善するため、設計者が設計を行う段階から参画するように変えていきたいです。どういう使われ方をしているかがわかれば、どんな部品が必要なのかもわかってきます。部品技術から使用部品を提案することで設計者が設計に専念することができ、我々も部品使用可否の審査の時間を市場調査の時間に変えられる。そうすると、Ohtsukaさんが言った市場調査も効率よく進められ、より価値のある情報を得られるのではないでしょうか。そういった形で、これからの宇宙機器開発により深く貢献できればと考えています。
Ohtsuka Hiromichi氏プロフィール
半導体業界で、液晶テレビや車載向けのアナログ設計に従事した後、日本電気株式会社に転職。
当社電源技術部で経験を積んだ後、現在は部品技術部にて、宇宙用部品の信頼性品質に関わる業務を担当。
プライベートでは3人の子供を育てる親として日々奮闘しながら、家族からの温かいサポートもあり、全力で仕事に取り組んでいる。

Hashimoto Akira氏プロフィール
新卒入社後、電気設計部門で人工衛星に搭載するセンサの評価やセンサ周辺回路の設計、サブシステム評価等を経験し、現在の部品技術部へ異動。
3児の父。日々の子供とのコミュニケーションを大切に、子育てと仕事の両立を目指している。
