サイト内の現在位置
生産プロセス ~生産技術~
人工衛星やロケットに搭載する機器(以下、宇宙機器)開発のため、設計者がさまざまな設計図や仕様書を作成する。しかし、それだけではすぐ製造には移れない。設計と製造の間には重要な工程がある。その工程を担い、まるで有名レストランの総料理長のように“ものづくり”全体をコントロールしていくのが「生産技術」だ。生産技術部門はどのような業務を担っているのか? また、生産技術部門で働く魅力とは?生産本部 生産技術部のOnoue Masayuki氏に話を聞いた。

宇宙機器製造のレシピを作るような仕事
「ひとことで言うと、設計から製造に移る間にあるのが、我々の仕事だと思っています」
Onoue氏は生産技術の業務内容をそう言い表した。加えて、中心的な業務は設計図を“ものづくりができる仕様書”に置き換えることで、「料理で言えばレシピを作るようなもの」と説明する。
「料理のレシピには“この野菜を何度で何分炒めなさい”とありますね。宇宙機器の設計工程から製造工程に移るためには、それと同じようなことを決めていく必要があります。例えば、“ここにはんだ付けをする場合には、はんだごてを何度に設定して、何秒以内ではんだ付けしてください”という感じです」
設計者から上がってきた設計図には、そのような指示は書かれていない。設計図さえあればすぐ製造にかかれるものではないのだ。
「評価」からスタートする生産技術の業務
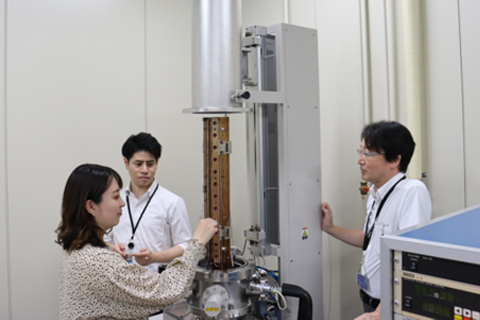
生産技術の中心的な業務はわかった。しかしその前後にも重要な業務がある。それが「評価」の工程だ。実は、生産技術の仕事は、材料と部品実装方法の認定を行う「評価」という工程からスタートする。
「評価」について、Onoue氏はこう説明する。一般的に料理においては、レシピを書く前に、各食材や調味料の特性や課題を知っておかなくてはならない。単に「これを使う」とレシピに書くのではなく、実際に煮こんでみたり、焼いてみたりして、自身で確かめておく必要があるだろう。「評価」で行うことも、これと同じだという。
設計者は設計図を書くときに「こういう材料を使いたい」と考えるが、生産技術の担当者は、設計者が設計に入る前に綿密にコミュニケーションを取り、設計者が使おうと考えている材料の特性や課題などを十分に知っておく必要がある。これが「評価」の工程で行うことだ。
「評価」を行ううえで気をつけていることをたずねると、Onoue氏からは、「製品のカタログ値を鵜呑みにしては失敗するので、あくまで自分たちで評価しています」との答えが返ってきた。宇宙機器の製造で使う部品は、温度や湿度などの環境によって、いろいろな変化が起きる可能性がある。
「ある樹脂を例にとると、120度を超えると一気に劣化するケースがあります。こういったことを把握し、自分たちで部品の特性を調べたうえで、“きっちりこの(温度の)範囲で作業してください”などと生産技術が指定しておかないとダメなのです」
また、「宇宙空間で使われる」という特殊な環境を考慮して、評価方法も生産技術が、きっちり決めておく必要があるという。
「例えばはんだ付けには、お客様から“宇宙空間で5年もつようにしてください”と要望があるとします。そうしたらその“宇宙空間での5年間”を模した試験をします。例えば、マイナス40度から100度の熱サイクル1000回が宇宙空間での5年経過と同等だとあらかじめ計算で出しておき、その条件ではんだ付けしたものを熱衝撃試験で1000サイクル回して、断線などがないことを確認しておきます」
万一不具合が発生したら、「5年間もつように」というお客様の要求が満たせなくなってしまう。不具合の兆候を事前につかむ「評価」の工程は極めて重要だ。
「宇宙では宇宙機器を直せません。“この作り方で100パーセント大丈夫”というところまで追い詰めて、数値を決めないと(宇宙機器は)作れません」
“ものづくりができる仕様書”の作成と設備導入

「評価」を経て、設計者から設計図が届けられたら、今度は「作業仕様書作成」という業務に入る。これが、冒頭でお伝えした“レシピ作り”の工程だ。具体的には、各設計者から上がってきた設計図を“ものづくりができる仕様書”に落とし込んでいく作業となる。ここでは前述したように、実際に製造に入るための細かい指示を加えていく。しかし、さらに大事なポイントがあるとOnoue氏は指摘する。レシピに沿って作業すれば、誰でも再現できるようにすることだ。
「極端な話をすれば、今日やって来た新人が そのレシピ、つまり仕様書を見て材料を投入すれば、ベテランと同じものが出てくるというのが理想です」
さらに生産技術は「設備導入」の工程にも関わる。中でも治工具の設計が大切な仕事になる。宇宙機器を製造するための治工具にはいろんな要素が求められるので、生産技術が設計することが多くなるとOnoue氏は話す。Onoue氏は現在管理職であり、直接手を動かす立場にはないが、キャリアの中で治工具づくりの仕事は好きだったと笑う。
「製造現場の人に“この治工具使いやすいね”と言われると、大きなやりがいを感じます。また、治工具が使いやすければ効率も上がり、コストも下がりますから」
Onoue氏のように、“ものづくり”の現場が大好きなメンバーが生産技術には揃っているのだ。
常に宇宙空間利用をイメージする心構え

さまざまな素材の特性や課題を把握し、100パーセント大丈夫というところまで数値を追い込むこと。また、設計者ともコミュニケーションを取りながら、“ものづくり”ができる仕様書(レシピ)にまとめ上げ、実際に製造に入るまでをコントロールすることが生産技術部門の仕事ということがわかった。
Onoue氏に、生産技術の仕事の楽しさ、おもしろさを聞くと、「製品が出荷され、人工衛星が組み上がり、宇宙に打ち上がった時はやっぱり嬉しい瞬間」との答えが返ってきた。打ち上げの瞬間は、自席でオンライン中継を見たり、場合によっては会議室に集まり、パブリックビューイングのように皆で見守ることも多いと、話してくれた。
逆に仕事で大変だったことはあるのだろうか。ここまで述べて来たように、総料理長的な重責を担う生産技術は、多くの関係者と関わる。また関わらないと仕事が進まない。しかしその中には、きびしい態度で接してくる関係者もいる。そんな関係者とのコミュニケーションに悩んだ時期もあったとOnoue氏は振り返る。そんな時、Onoue氏が心がけたのが「冷静さ」だ。
「相手方は何を欲しているのかを冷静に考えて、欲しがっている情報を出していくことが重要です」
冷静に相手のニーズを把握し、情報を出していくうちに相手の対応が変化して、一目置かれるようになり、良い関係に変わったという。
「“この人はちゃんと答えてくれるな”という信頼関係が生まれ、あえて私に意見を求めて来るように関係が変わりました」
今、管理職として、若手メンバーにはそういう経験を伝えて行きたいと言うことだ。
厳しい条件を現実的に「可能なやり方」に落とし込むスキル
これまでのキャリアの中、どのようなスキルや知識を身につけたのか。Onoue氏は、「実装が非常に難しい部品の実装工法の確立や、その信頼性の検証方法。また、客先への報告のやりかた」と話す。少しかみ砕いて話してもらうと、そもそも宇宙機器の製造には、顧客から厳しい作業規程が課せられる。それはもちろん順守していくべきものだが、それをすべて順守しては、会社としてコストが合わない、スケジュールを守り切れない場合があるという。
そして、そこからがOnoue氏の腕の見せ所だ。自身の経験や知識をフル回転させ、その作業規程について、「現実的に可能なやり方」を考案し、顧客に逆提案することもあるという。いわば、お客様の要求の本質を理解した上で現実的な形に落としこむスキルというわけだ。
しかしそれはスキルというより、長年かけて醸成した信頼関係によるところが大きいかもしれないと振り返る。Onoue氏は、普段から相手が出してきた質問に真摯に対応して、人間関係や信頼関係を築いてきた。日頃から何気ない質問でもなるべく早く返す。そうすると、自分が困ったときや、何気ない問い合わせにも、早く答えを返してくれるようなコミュニケーションが取れるようになっていくとのことだ。
宇宙機器の“ものづくり”を変革していかなくてはならない
今、Onoue氏が新人だったら、どんな言葉をかけるかと聞くと、「今扱っている製品や技術はそのうち無くなるか、まったく違うものに置き換えられる。それに気づき、新しい”ものづくり”を受け入れ、現場を変えていけるエンジニアになってほしい」と話す。人工衛星も低コストの時代に入っており、日本は立ち遅れている部分があるという。
「今までと同じような宇宙機器の“ものづくり”をしていると、納期もコストも合わなくなるのです。民生製品の工場見学に積極的に行くなど、宇宙機器以外の“ものづくり”もしっかり見た上で、今の仕事に取り組んで欲しいと言いたいです」
今後、Onoue氏は民生の“ものづくり”の仕方を宇宙機器に活用していきたいと語る。自動化はもちろん、設計をどうするかまで踏み込みたいということだ。
NECスペーステクノロジーには、Onoue氏を始めとして、宇宙機器開発のイノベーションを進めようとしている技術者が集まっているのだ。

Onoue Masayuki氏プロフィール
T工業高等専門学校 電気工学科卒業
NECグループ会社に新卒入社後、主に放電管の生産技術に従事。
約10年前に移籍。現在は、衛星やロケットに搭載される機器の生産技術に従事し、日々、製造現場の改善に取り組んでいる。
最近は運動不足ぎみなので、ゴルフやテニスなど再開したいと思っている。
