サイト内の現在位置
設計プロセス 〜構造設計〜
人工衛星やロケットに搭載する機器(以下、宇宙機器)は、 “機能”を担う機器だけで構成されているわけではない。宇宙機器の“箱”となる筐体や、宇宙機器に電気を供給する電気部品も、宇宙機器に欠かせない構成要素となっている。この筐体の構造設計と、内部電気部品の実装設計を行うのが「構造設計」の役割だ。
構造設計とはどのような業務なのか?構造設計の魅力とは?構造設計者のMohri Masahiro氏に話を聞いた。

電気設計者が考えた機能を具現化する仕事
「構造設計とは、簡潔に言うと、宇宙機器の機能を考える電気設計者が頭の中で考えていることを、具現化する仕事です」
構造設計の仕事内容についてたずねると、Mohri氏はこう説明し始めた。宇宙機器の開発では、まず電気設計者が、宇宙機器で実現したい機能を考える。この電気設計者の考えをもとに、その機能を実現できる“形”に筐体を設計し、パズルのように内部電気部品を配置していくのが、構造設計者の役割だ。ただし、構造体を自由に設計できるわけではない。まず、厳しい宇宙の環境に耐えなければならない。さらに、「もっと小さく」「もっと軽く」などさまざまな要求や制約がある中で、“最適解”を模索していくのが構造設計者の主たる仕事だという。
「構造設計の仕事内容を身近なもので例えると、ブロック玩具に似ています。ブロックで家や乗り物を作るときには、持っているブロック数に制限がある(大きさや重さに制限がある)中で、どこにブロックがあれば壊れない強度を保てるか?どこにどのくらいの空間を設けるべきか? 人や物はどこに置こう? など考えながら遊ぶのではないでしょうか。私は普段の複雑な業務の場面においてもそのように単純化し、シンプルに思考するように心がけるようにしています」
構造設計の仕事は「5つの工程」に分けられる
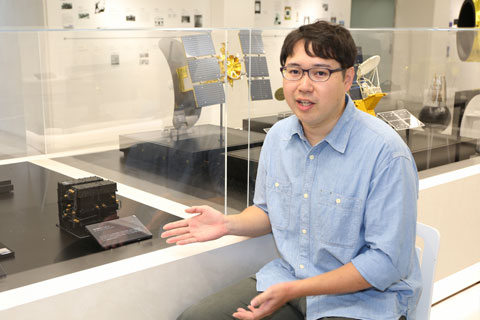
では構造設計には、具体的にどのような工程があるのか。Mohri氏は、構造設計の仕事を「5つの工程」に分解する。
1つ目が、電気設計者の要求を理解する工程(工程1)だ。構造設計者は、まず電気設計者と密にコミュニケーションを取り、「どんな機能を実現したいのか」を正確に捉えていく。2つ目が、電気設計者からの要求を“形”に落とし込む筐体設計・実装設計(工程2)だ。この時点で大きさや重さの最大値が定められているため、その中で、筐体の形や電気部品配置の最適解を探すことになる。
構造物の形がおおむね決まると、その構造物が、宇宙の環境に耐えられるかどうかを、コンピューター上でシミュレーション(構造・熱・放射線解析)する工程(工程3)に移る。これをクリアすると、設計したものが実際に作れるかどうかを生産現場(機器製造検査部)や社外の加工・製造メーカーに確認(工程4)したうえで、最終的に図面化(工程5)し、ようやく生産現場に製作を依頼することができる。
5つの工程のうち、特に時間がかかるのはどこだろうか。この質問に対してMohri氏は、「やはり2つ目の筐体設計と実装設計の工程に大きな時間がかかります」と頭をかきつつ教えてくれた。
「電気設計者からの要求は、簡単に実現できるものばかりではなく、非常に難しい要求が含まれる場合もあります。そんなときは制約が多い中で何とか最適解を模索せねばならず、どうしても時間がかかってしまいます。大変ではありますが、同時に構造設計者としての腕を試される場面でもあり、大きなやりがいを感じる工程です」
「社内外のあらゆる人」と一緒にする仕事

構造設計は設計プロセスの「中間」に位置する。このため構造設計者は、「社内外含め、あらゆる人と一緒に仕事をすることになる」という。
「電気設計者とは、『この機器で何をしたいのか?』について白熱した議論を交わすこともありますし、自分が考えた筐体(構造体)が本当に作れるのかを社内の生産チームや社外のメーカーに確認する際に、『これは作れないよ』とフィードバックをいただくこともあります。構造設計の仕事は、さまざまな人の意見を吸収し、支えられながら行うものだと考えています」
多様な専門家とのやりとりが発生するということは、当然、コミュニケーションを円滑に進めるための工夫も必要になるだろう。Mohri氏が重視しているのは、「Face to Faceのコミュニケーション」だ。
「構造設計者の仕事は相手にお願いをする立場になることが多く、電話やメールだけで伝えると、受け取った側の状況も分かりませんし、依頼内容の詳細や真意が伝わりづらい場合があります。ですから、何か相談事があるときは、極力会いに行くようにしています。宇宙機器の開発現場を支えているのは、各工程の現場の“人”です。相手に敬意を持ち、少しでも相手が気持ちよく対応できるよう心がけています」
最適解を思いついた瞬間の達成感が、やみつきに
Mohri氏は、構造設計の仕事のどこに魅力を感じているのだろう。この質問には、「要求された機能を満足する最小・最軽量の設計を考えついた瞬間の達成感が、やみつきになります」と目を細めながら答えてくれた。
「設計中は、『あれをどうしよう』『ここをどうしよう』と四六時中考えている状態で、頭の中にずっとモヤモヤがあります。最適な設計を考えついた瞬間には、このモヤが一気に晴れ、ものすごく清々しい気持ちになります」
さらにこの達成感が、社内外のさまざまな情報をアンテナ高く吸収するモチベーションとなり、「自身の知見や技術を高める“好循環”にもつながっている」という。

もう一点、製造部門を海外に移している企業が多い中、NECスペーステクノロジーでは、製品の高品質・高信頼性を担保するため、社内で機器製造しているが、「この点も大きな魅力」だと、Mohri氏は子どものような笑顔を浮かべ語ってくれた。
「実は私が当社に入社した大きな決め手の1つは、社内に生産部門があったこと。自分で設計したものが作られる様子を間近で見られることは、ものづくりが好きな人間にはたまらない環境なのです」
辛いこともある、でもそれはおもしろさと表裏一体

大きな達成感が得られる一方で、構造設計は設計プロセスの中間に位置するため、「お客様からの要望が難解な場合は、時間と費用を十分使えず、苦しむこともあります」という。
宇宙機器は全体スケジュールが決まったうえで開発がスタートする。しかし、お客様の要望が難解なものである場合、機能を考える電気設計フェーズにどうしても時間がかかってしまう。そうすると、電気設計の後工程である構造設計や機器製造検査で十分な時間と費用が使えなくなる場合もあるとのことだ。
だが、そうした厳しい状況も、社内の先輩・上司・同僚や社外のメーカーの担当者が親身に相談に乗ってくれ、効率化に関する助言や自身が持つノウハウを惜しげもなく授けてくれたことで乗り越えられているという。ときにはお客様であるJAXA(宇宙航空研究開発機構)の担当者がアドバイスをくれることもあり、「非常に助かっています」とMohri氏は感謝の思いを語る。
「『辛い』と言いましたが、それはおもしろさと表裏一体でもあります。周りの人の助言やこれまで培ってきたノウハウを総動員して、問題を解決したときには、やってきてよかったなと心から思います」
若手時代の大規模プロジェクトの経験が大きな成長につながった
そんなMohri氏が、これまでで最も印象に残っていると話すのが、「あるプロジェクト内で、電力制御器(PCU)と電力分配装置(PDU)を開発した仕事」だ。まだ数種の設計しか経験したことがない新人のときに任されたのが、構造設計者がMohri氏とOJT(現任訓練)の上司の2人なのに対し、電気設計者は6人も就くという大がかりな宇宙機器の開発プロジェクトだった。
「通常は電気設計者も2人程度なのですが、それが6人ともなると要求そのものの件数や要求調整にかかる時間はかなりのものでした。毎日が台風のような状況でしたが、何とか最後まで乗り切り、最終的には構造上の不具合ゼロで開発を完遂することができました。実はその製品は、現在も繰り返しリピート生産されています。そんな重要な製品の開発に携われたことを今も誇らしく思っています」
新技術にアンテナを張り、宇宙機器をさらに進化させたい
今後構造設計者の仕事をしていくうえで大切なことは何かと聞くと、Mohri氏は即座に、「アンテナを高くして、新しい技術を取り入れる姿勢」と答えてくれた。現在、さまざまな領域で技術革新が急速に進んでいるが、その一方で、宇宙領域では、旧来の技術を用いている部分も多く、「新技術にアンテナを高く張ることで、宇宙機器のさらなる進化につなげられる」とのことだ。
宇宙空間のビジネス活用が活性化する中、宇宙機器開発に寄せられる期待はますます高まっている。NECスペーステクノロジーでは、そんな期待に応えるべく、開発現場の思いが込められた、高信頼、高性能な宇宙機器をこれからも開発していく。
Mohri Masahiro氏プロフィール
H大学 大学院工学院 機械宇宙工学専攻 修了
大学院では超小型衛星の熱設計に関する基本研究に従事。CanSat(空き缶サイズの模擬人工衛星)の設計/製造や小型ロケットの打ち上げにもかかわる。
新卒入社後、人工衛星搭載機器の構造設計に従事。衛星、ロケット問わず、日々様々な機器の設計、解析に取り組んでいる。プライベートでは1児と1匹の父。帰宅後に子供と犬からその日あったことを聞くのが楽しみ。いつか犬と話せればいいなと思っている。
