サイト内の現在位置
搭載機器の開発 ~電源~
私たちの身の回りにあるもののほとんどが、動くためにエネルギーを必要とする。エネルギー源として人工衛星やロケットなどの宇宙機の一生を支え続ける、それが「電源システム」である。
宇宙機の電源システム、それを構成する機器とは?また、その開発と設計エンジニアとして働くことの魅力とは?
電源機器エンジニアのMori Daisuke氏に話をきいた。

動物の一部に例えると“おなか”
エネルギーを作り出し、蓄え、いつでも動けるように管理する
人工衛星の「電源システム」は、主に太陽電池パネル、バッテリー、電力制御器で構成される。
太陽電池パネルは、宇宙で降り注ぐ太陽光エネルギーを電力に変換する。
バッテリーは、太陽電池パネルに光が当たらず、電力を作り出せない時間帯に備え、電力を蓄える。
そして、バッテリーの充電と放電を管理し、電力を必要とする人工衛星内の各機器に電力を分配するのが、電力制御器である。
「皆さんは『電源は心臓』みたいなイメージがあるかもしれません。でも、僕にとっては『電源はおなか』のイメージです。おなかが空いちゃったら何もできませんからね」
人工衛星も私たち人間や動物と同じで、おなかが空いてエネルギーがなくなるとパフォーマンスが落ちたり、最後には動けなくなったりしてしまう。さあこれから働くぞというタイミングで、動けません…とならないように、人工衛星全体のエネルギーの収支バランスを管理、運用する、それが「電源システム」の役割である。
泥臭く、とことん向き合い、理解する
電源システムの機器に限らず、人工衛星に搭載する機器の設計業務は多岐にわたる。機器を担当するエンジニアが自身で設計することもあれば、他の設計部門に要求を出したり設計結果の確認をしたりもある。機器の構想段階から製造完了までほとんどすべての工程に関わっている。
機器全体の設計も、機器を構成する回路の設計も、一つひとつが、検証の積み重ねだ。また、図面を描くにも解析をするにも情報をきちんと準備し、整理しなければならない。結果に到達するまでには、地道な作業が続く。エンジニアが、自分の担当する機器にとことん向き合い、些細な作業であっても一つひとつの意味を理解するプロセスを積み重ねることで宇宙という厳しい環境でも安定してパフォーマンスを発揮する機器が完成するのだ。
気が遠くなるような道のりに思えるが、Mori氏は、
「地道で泥臭い検討や作業は大変なんですけど、表面的な理解で進めてしまうより、一つひとつをきちんと理解したうえで進めるのが自分としては好き」という。
開発はチーム
高い技術をもつ個性豊かな人々の連携で、カタチになっていく
機器開発はMori氏のような機器担当エンジニア1人で行えるものではない。温度や放射線など地上と比べてはるかに厳しい環境でも電子機器が動作するように、ロケットによる打上げ時の振動や衝撃に耐えられるように、また、お客様の開発スケジュールどおりに順調に進められるように、NECスペーステクノロジーでは様々な専門チームが活躍している。
機器担当エンジニアはお客様の要求に応えられるように、専門チームと密に連携し、関係者全員で担当機器に向き合っている。構造を設計するチーム、開発スケジュールを管理するチーム、機器として仕上げる技能を持ったチームなど、全てのチームが高い専門性をもつプロ集団である。
「皆さん各分野のプロフェッショナルなので、内容についていくのも大変で、苦労することも多々あります。でも大変であればあるほど、得られることや学びも多いと感じています」
Mori氏はそう言いながら、目を輝かせた。

わかった、できた、もっと知りたい
その連続
さらにMori氏は続ける。
「わからなかったことがわかるようになった、新しい発見があった、その発見から芋づる式に、周辺領域のこともわかるようになるので、その発見を基にしていろいろと試してみたくなってしまいます」
新しい機器の開発や新しい技術の取り込みは苦労の連続で、寝食を忘れるほど頭がいっぱいになったり、なかなか解決策が見出だせない中で期限が迫ってきてプレッシャーを感じたりで、決して楽ではない。しかし、困難を乗り越えてしまえばあとに残るのは、探求心や好奇心。それらが次なる挑戦への活力となる。
「要素検討からスタートする新規機器の開発・設計は、泥臭いことが多く、楽しいだけじゃないとわかっていても携わりたくなります。大変であってもその中で得られる面白さがあるからです。電源機器エンジニアとしてのコア技術を成長させつつも、FPGAなどデジタル関連の技術の経験も積んで、エンジニアとしての裾野を広げ、いろいろな電源機器や電源システムの開発に携わっていきたいです」

ロケット向け電源システムの機器開発
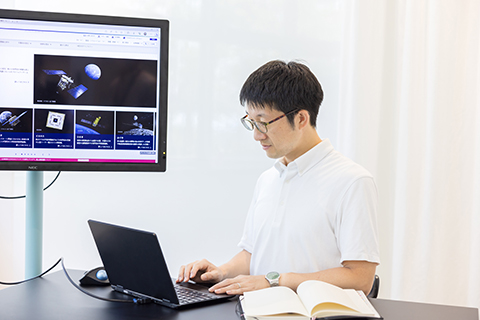
そんなMori氏が現在取り組んでいるのが、新型ロケットの電源システムの機器開発だ。求められる機能も性能も、お客様も仕事の流れも、人工衛星のそれとは異なる。NECスペーステクノロジーにとっても、新規の事業領域での機器開発である。
ロケット搭載機器は、機器の運用や安全性設計への考え方が衛星とは異なる。ロケットが安定して飛行できるように、また、異常の際は安全かつ確実に飛行を中断できるように様々なことを考えなければならない。競争力強化のための工夫として、従来の宇宙用部品だけではなく、民生用部品も積極的に採用している。
Mori氏は入社以来、いくつかの衛星搭載機器を担当してきた。しかし、それらの機器は過去の設計資産を活用したものが多く、新規開発は経験がなかった。さらに、社内の異動で二年間設計業務から離れ、再び設計業務に戻ったときに任されたのが、ロケットの電源システムの機器開発だった。
領域が違えば、得られる学びも身につくスキルも異なる。電源に関する基本的な知識に加え、機器の運用やシステムを含めた知識が、設計技術として身についた実感があるという。また、業務を通して興味の幅が広がり、それまではあまり興味のなかったロケットに、いまでは興味津々。
「時間のあるときには世界各国のロケットの打上げライブやVtuberのライブ配信を見てみたり、論文を読んでみたり、最近では打上げビジネスに興味が広がっています」
宇宙ビジネスを支える
NECスペーステクノロジーの電源システム
宇宙データ利用や通信インフラとしての宇宙機活用など、宇宙空間を使ったビジネスが加速している近年。新たな市場参入者や投資も増え、技術革新も進み、今後ますます宇宙は身近になっていくだろう。
様々なサービスが計画されているが、すべて人工衛星やそれを打ち上げるロケットの電源システムが正常に動作してこそ実現される。
私たちのために働いてくれる衛星とロケットが、おなかいっぱい、元気いっぱいでいられますように…
そんな願いを込めて、NECスペーステクノロジーはこれからも、宇宙機、そして宇宙機によるビジネスを支える電源システムを開発していく。
Mori Daisuke氏プロフィール
N大学大学院理学研究科卒業
大学院では赤外線検出器の研究に従事。
新卒入社後、人工衛星のシステム電源用機器の設計や搭載機器用電源の設計に従事。途中2年間品質保証業務に従事したのち、再びシステム電源の機器を担当する部署に戻り、ロケットに搭載される機器の開発に取り組んでいる。プライベートでは2児の父。夫婦共働きで日々てんやわんや。いつか子供たちと一緒に、自分が関わったロケットの打上げを見に行きたい。
