サイト内の現在位置
設計プロセス 〜FPGA設計〜、技術継承
人工衛星やロケットに搭載する宇宙機器にはさまざまな部品が使われている。そうした部品のうち、基板や機器の中を行き交う電気信号の処理を担っているのが集積回路だ。集積回路が正しく機能しないと、宇宙機器や人工衛星全体の機能損失にもつながりかねない。NECスペーステクノロジーにおいて、集積回路の一種であるFPGA(Field Programmable Gate Array)の設計や、集積回路に搭載するソフトウェアの設計を担っているのが第三搭載技術部だ。
今回は第三搭載技術部において、集積回路の一種である「FPGAの設計」と、測位衛星からの信号を受け取るGNSS受信機に関する「技術継承」に取り組んでいるI. Daichi氏に、両業務の内容や魅力を聞いた。
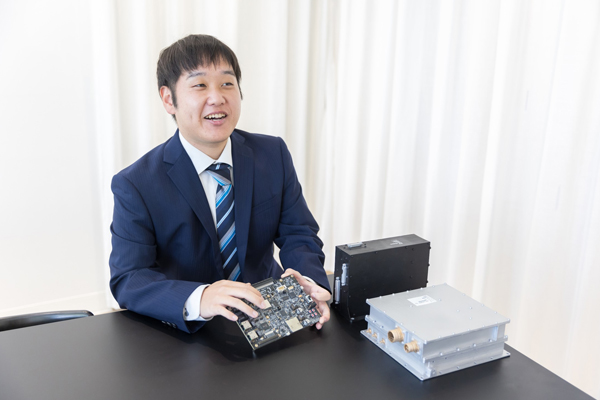
“単純な計算”の組み合わせで“複雑な処理”を実現
集積回路にはいくつかの種類がある。そのうち、パソコンやスマートフォンなどにも使われ、一般にも聞き馴染みがあるのがCPU(Central Processing Unit)だろう。宇宙機器にも使われており、第三搭載技術部の中にもCPUを動作させるソフトウェアの設計を担うチームがある。ただ、CPUは基本的に一度に1つの計算しか処理できないという弱点がある。それに対して、チップ内に並列して走る回路を自由に構成でき、一度に複数の計算処理を行えるのがFPGAだ。処理能力の高いFPGAのチップは、宇宙機器の基板に実装され、主に機器内を行き交うさまざまな電気信号を処理する。
このFPGAの機能を実現するための回路を設計するのが「FPGA設計」だ。Daichi氏によると、「FPGA設計」の大まかな業務工程は以下のようになる。まず電気設計グループから「こういう処理をするFPGAを作ってほしい」といった要求を受ける。次に、その要望の内容を理解した上で実現する回路を思い描き、足し算や掛け算レベルの極力簡単な処理に切り分けていく「検討作業」に入る。続いて、これらの計算処理を組み合わせてコードを作成(「コーディング」)し、最後に「やりたいことを達成しているか」「消費電力などの制約を満たしているか」などを確認する「検証作業」を行う。完成したコードは次の製造検査工程でFPGAに書き込まれ、FPGAが実装された基板の電気調整へと進む。なお、Daichi氏自身は、これら業務のうち「検討作業」と「コーディング」を主に担当しているとのことだ。
Daichi氏に「FPGA設計」の仕事を身近なものに例えてもらうと、「ドミノ倒しに似ている」との答えが返ってきた。
「ドミノ倒しは、ドミノが次々と倒れていく単純な運動の連続です。でも色の違うドミノを組み合わせることで、最後に複雑な絵の模様を表現することもできます。FPGAも、足し算や掛け算など単純な計算処理の組み合わせで構成されており、これら単純な処理をうまく組み合わせることで複雑な処理を実現します。この“単純なものの組み合わせで、複雑なことを実現する”ところが似ていると思います。ただし、両方とも全体像を意識しながら作業を進めないと、組み合わせを間違ってしまい、期待する挙動とは異なってしまいます。こうした難しさがある点も似ていると思います」
座学と実践の両輪で進める「技術継承」

もう1つ、Daichi氏が取り組んでいるのが「技術継承」だ。NECスペーステクノロジーでは、測位衛星からの信号を受信するGNSS受信機を開発・製造しているが、Daichi氏はその仕組みについて、長年開発に携わっているエキスパートから教わっている。
「宇宙用のGNSS受信機は、一般的なものとは異なる作りとなっています。この仕組みがとても難解であり、開発を長年担当してきたエキスパートの方と同等レベルで概念設計できる人が社内にほとんどいません。そこで社内の技術を絶やさないために、私ともう一人の担当者がペアで、その技術を継承しています。」
具体的には、まずDaichi氏がエキスパートから受信機の仕組みについて教わり、その教わった内容をもう一人の担当者と共有する。そして、もう一人の担当者がFPGAのコードを作成し、Daichi氏がそのコードの検証などに活用するGNSS受信機の動作を模擬したシミュレーションツールを作成している。こうした座学と実践的な開発業務を組み合わせることで、しっかり身につくように「技術継承」を進めているとのことだ。
「『技術継承』の業務は、研究室のゼミに似ています。まず私がメインでエキスパートの方にいろいろ教えてもらい、その内容について私がどれだけ理解したかを、エキスパートに確認してもらいます。その上で、ペアを組んでいた人に教わった内容を共有しています。これは、まさに教授から指導してもらい、その内容を研究室のメンバーに説明する研究室のゼミの流れと同じです。『技術継承』は私自身の知識欲も大いに刺激される業務となっています」
「理解の深まり」を実感できることが楽しい

ではDaichi氏は「FPGA設計」や「技術継承」のどこに魅力を感じているのだろう。まず「FPGA設計」では、「コーディング」のときに自分が意図していた通りに動くと、「とても気持ちが高揚します」と嬉しそうに話してくれた。
「一般的なプログラミング作業でも、コードを書き、その動きを試した際に一度でうまくことは少ないですよね。FPGAもそれと同じです。うまくいかない原因を突き止めて修正を加え、思い通りに動いたときには、やはり大きな達成感を覚えます」
「技術継承」については、GNSS受信機は非常に複雑な理論をベースにした技術であり、「その理論に対して少しずつ理解が深まっていくことを実感できて楽しい」と話す。
「GNSS受信機の理論は非常に難解であり、最初は何が何だかわかりませんでした。しかし、少しずつ理解が進むと、これまでわからなかったことが一気に理解できる瞬間が訪れます。このときに自分自身の成長を感じて嬉しくなります。ただ、その理解したことを深掘りすると、すぐにまたわからないことが出てきてエキスパートに質問をするのですが。それでも自分が前に進んでいることを実感でき、大きなモチベーションになっています」
“大変さ”と“やりがい”は表裏一体
さまざまな魅力がある一方で、「FPGA設計」や「技術継承」には大変な一面もあるという。
まず「FPGA設計」においては、先述した通り、コードの書き始めでは意図通りの動作をしてくれないことがあり、「すぐには原因がわからないときは大変」とのことだ。
「特に、プログラム内のバグを見つけ修正する作業は私にとってはまだ簡単ではありません。作業が行き詰まったときは、同じチーム内の先輩に自分が書いたコードをレビューしてもらい、おかしな箇所を指摘いただくことで、何とか軌道修正しています」
「技術継承」については、エキスパートの説明の中にDaichi氏が知らない専門用語や概念が次々と登場するため「理解が追いつかないところがある」点が大変だという。
こうした状況に対処するため、単に教えてもらうのではなく、前回教わった箇所について、Daichi氏が理解した内容をエキスパートに伝え、その内容に間違いがあれば指摘してもらうサイクルを採用してもらったとのこと。これにより、Daichi氏の理解が深まり、「技術継承」がスムーズに進むようになったという。
「『大変』とお伝えしましたが、いずれも楽しさと表裏一体です。確かに大変な一面もありますが、頑張れば乗り越えられる“壁”ばかりです。特に『技術継承』については、私自身が苦労した分、わからない人の気持ちがわかると思います。自分が得た知見を他の人に伝えるときに、よりわかりやすく伝えられるぞという自信にもつながっています。どちらの仕事にも、大きなやりがいを感じています」
学会発表経験がモチベーションアップのトリガーに

Daichi氏はもともと通信機器の電気設計を担う第一搭載技術部に所属していたが、2年ほど前に第三搭載技術部に異動した。異動からそれほど年数は経っていないが、いくつか強く印象に残る経験をしたという。その1つが「海外での学会発表」だ。
「それは、私がGNSS受信機について教えてもらっている方とは別のエキスパートが、ある論文を書き、若手に発表する機会を与えてくれたものです。運良く海外の学会で発表する機会を得て、そのときに社外のエンジニアや研究者など多くの方と交流することができました。この経験が非常に刺激的で、『もっと研鑽を積み、こういう場で発表できる人間になりたい』という技術力向上へのモチベーションアップにつながりました」
学会発表を経験した後、Daichi氏は日々勉強に努め、関連知識を吸収するようになったという。この姿勢は、入社当時の自分自身に伝えたい言葉を訪ねた際の「成長に貪欲であるべし」というDaichi氏の言葉にもあらわれていた。
「絶対に損はしないので、今のうちに英語を徹底的に勉強しておいてくださいと伝えたいですね。なぜなら海外関連の仕事には、やはり英語ができた方が参加するチャンスをいただきやすいですから。とにかく今は自分のいろんな可能性に対して『チャンスを逃したくない』という思いが強くあります」
将来はGNSS受信機分野のトップへ
最後に、今後どういったことに力を入れたいかと聞いた。するとDaichi氏は「GNSS受信機の分野でトップに立ちたい」と力強く答えてくれた。
「『技術継承』で取り組んできたGNSS受信機の分野でトップに立てるような開発者になりたいです。そのためにもまずは理論、知識を深め、さらにFPGAやCPUの使い方にも精通して効率的な設計ができるようになり、最終的には自分自身が中心となり、高精度で安価なGNSS受信機を開発できるようになりたいです」
現在、宇宙業界はベンチャー企業やスタートアップなどの新興企業の台頭が著しい。しかし、そんな変革の波が押し寄せる中でも「NECスペーステクノロジーで身につけた技術や知見があれば、自分の立ち位置を見失うことなく活動できる」と、Daichi氏はものづくり現場で長年培われた技術や知見の“強さ”を訴える。
そんな現場メンバーの向上心や思いに支えられながら、これからもNECスペーステクノロジーでは高品質、高精度な宇宙機器が生み出されていく。
I. Daichi氏プロフィール
H大学大学院工学院エネルギー環境システム修了
大学院では数学手法を用いて大規模データから目的に必要なデータを効率的に抽出する研究に従事。
新卒入社後は電気設計部門で人工衛星に搭載されるコマンド受信機の設計を経験し、現在の第三搭載に異動。
休日はひたすら自転車を漕ぎ、体力の限界に挑戦している。
